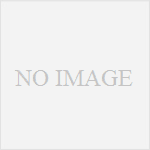誰も知らない/是枝裕和監督

誰も知らない是枝裕和監督
1988年に発生した巣鴨子供置き去り事件が題材らしいが、それはあくまでもモチーフであり、実際の事件はとは必ずしも一致しているわけでもないということだが、しかし、かなり強烈な印象の残す作品だ。後味が悪い。この後味の悪さ、気持ち悪さ、やるせなさ。それだけ映画に力があるということなのだが、たとえモチーフだけだったにせよ、このような事件が実際にあったということはものすごく悲しいし、また一方で、こういうことは実は今でも、どこでも起きている起きえることなんだというリアリティも伝わってくる。
まずもって、子供達の生活風景がリアルだ。他愛のないやりとりや、ちょっとした仕草、子供の自然がそのままに切り取られている。母が失踪してから、徐々に廃れていく部屋や汚れていく子供達、一方、子供たちの成長も早く、明の声変わりや反抗期など、直接わかりやすく説明的に描写されるわけでもないが、それが兄弟の会話や対応などから伝わってくる。このあたりの話法の巧みさ。さすが是枝監督だ。
作品のなかで「手」とくに「指」が特別な意味をもった記号として扱われているように思えた。
オープニングで、アタッシュケースをいたわるようにさする明の汚れた手と指。長女の京子は母にマニキュアを塗ってもらうが、そのマニュキュアを勝手に使おうとして瓶を落としこぼしてしまう。この時、母は京子に怒る。これが直接の原因ではないことはもちろんだが、その後、母は失踪する。床にはこぼしたマニキュアの汚れ、京子の指には剥がれ落ちたマニキュアが母の不在の証明のようにクローズアップされる。
知り合った女子高生紗希から缶ジュースを貰って帰る明。缶ジュースを空に投げたは受け止める手のシーン。つかの間の喜び。自分たちを「知」ってくれる唯一の存在との接触。ゆきの命を救おうと万引きを試みようとするその瞬間の明の手の震え。そして、ゆきの最期。ここでも手が象徴的なものとして登場する。明は冷たくなったゆきの手を「気持ち悪かった」と言う。
母が面倒を見て、マニキュアまで飾ってくれた指。土で汚れた指、そして最期の冷たくなつた手と指。全編を通じて、手が不在や生きること、子供たちの心理や時間経過の重要なキーとして利用されている。下手に子供たちに苦しさや悲しさ、厳しいさなどを語るために表情をつくったり、セリフを用意するのではなく、重要なところでは「手」に語らせることで、子供の生々しさが軽減され、その分だけむしろ余計にリアリティが強化されているのではないだろうか。
スポンサーリンク
スポンサーリンク