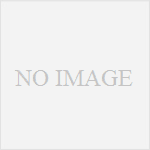ドアノー写真展とアヴァンギャルド・チャイナ、そして新国誠一
土曜日は京都駅伊勢丹のギャラリー「えき」でロベール・ドアノー写真展を観た。
ドアノーのスナップショットにはどこかユーモアが溢れている。ブレッソンと比較されることも多いようだが、ブレッソンがより決定的瞬間、かけがえのない瞬間を切り取ろうとしていたのに対して、ドアノーはもっと演出を凝らし、被写体との協力関係をベースとして日常を切り取っているように思える。もちろん、有名なパリ市庁舎前のキスなどは、ブレッソンの水たまりを飛び越える男の写真以上に「決定的瞬間」であるが、良い意味でより劇画的、演出っぽく見える。そこがむしろドアノーの魅力なのだろうか。
ドアノーのはこんなことを言っている。
「ローライフレックスを使うと、カメラの上からのぞき込む姿勢になる。つまり、正面から人々を見なくて済む道具なのだ。どんな猿の調教師も同じことを言うだろう:「動物と目を合わせてはならない」と。人間にしても同じことだ。正面から見つめるのは挑発と同じだ。ローライフレックスの、なんと礼儀正しく、慎み深いことか。カメラを身体の中心で構えるので、被写体を捉えるためには、背中を曲げなければならず、これが被写体に敬意を払っているような形になる」
ブレッソンがライカを愛し、自身の視覚の延長としてライカを位置づけ、自身の目が物事を捉えるような仕方で撮っていったのに対して、ドアノーはローライフレックスで対象物への敬意を表しながら撮影する。このあたりにも同じようにパリの日常や人々を切り取ったスナップショットの名手二人の違いが現れているようにも思える。
日曜日は、国立国際美術館 NMAOに「アヴァンギャルド・チャイナ」という現代中国アートの企画展を観に行った。
これは本当に素晴らしかった。期待していた以上の内容で、ここ最近見たあらゆるアート展の中では飛び抜けて刺激的で、且つ面白いものだった。こんな素晴らしい展示はそうはないと思うので現代アートに興味ある人はぜひ足を運んでほしい。(しかも、むちゃくちゃ空いてる)
「アヴァンギャルド(前衛)」という言葉がすでに埃をかぶってしまい、その言葉を持ち出すこと自体が多少の恥ずかしさや前時代感さえ漂う日本や欧米に対して、中国の現代アートにおいては、まさに「アヴァンギャルド」という言葉が極めてぴったりきて違和感がない。どの作品も、中国の政治状況や表現のおける制約などをコンテクストとして、表現することそのものが「前衛」でしかありえないという切迫さや緊張感がみなぎっている。
展示されていたどの作品も興味深かったのだけれど、特に「大家庭」シリーズの張暁剛(ジャン・シャオガン)と、無機質で漫画的な奇妙な男を描く方力鈞(ファン・リジュン)の2人の作品には圧倒された。この2人の作品を見るだけでも来たかいがあったと思えるぐらいに強烈だった。
張暁剛「大家庭」シリーズに漂う不安感や不安定感、頼りなさは何なのだろうか。1960〜70年代に中国各地の写真スタジオで撮られた「家族」写真をモチーフにして描かれた絵画作品だが、そこに描かれているのは明るく楽しい理想の「家族」の姿とはほど遠い、「家族」の表層性や脆さ、そして不気味さだ。赤い糸で繫がる人々。その赤い糸の細さがより一層、家族の記号性を暴露するかのようでもある。もちろん「家族」とは血縁関係上の家族だけではなく、毛沢東を父とする公的な「家族」の意味もあり、この二重化において、これらの作品がもつ独特の抑圧的ムードはより批評性を帯びるのだ。
方力鈞の絵画もその奇妙さ、けだるさに惹き付けられる。彼の作品は「シニカル・リアリズム」と称されるそうだが、まさに「現代」特に中国の現代をシニカルな視点で捉えたものだ。天安門事件においての民衆の自由主義運動の挫折以降、彼の作品の人々からは表情がなくなり、無機質でのっぺらな人物になっていったとされる。
他、孫原(スン・ユァン)と彭禹(ポン・ユウ)の「13組の電動車椅子とそれに乗った人物大の樹脂製の人形」のスケールの大きさ。電動車椅子がたてるむなしい音の響き、決して動かない人々。ゆらゆらと無目的、無規則に動く人形達の不気味さたるや。言葉では言い表せないような奇妙な感覚を味わうだろう。
同時に開催されていた「新国誠一の<<具体詩>>詩と美術のあいだに」。これもまた素晴らしかった。
コンクリート・ポエトリーについて殆ど知識を持っていなかったが、この展示を見て、一気に興味が沸いてしまった。