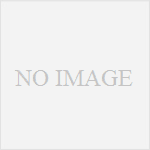ルーシー・リー展の感想
 先週の日曜日(2月6日)は、淀屋橋にある大阪市立東洋陶磁美術館に、ルーシー・リー展を妻と行ってきた。
先週の日曜日(2月6日)は、淀屋橋にある大阪市立東洋陶磁美術館に、ルーシー・リー展を妻と行ってきた。
14時過ぎに美術館についたのだが、予想以上の長蛇の列ができていてびっくりした。係の人によると、平日や休日でも午前中なら空いてるとのこと。ルーシー・リーってそんなに人気なのか。テレビや雑誌で特集でもされたのだろうか。
並ぶのは嫌いだけれど、その日は比較的暖かくもあったし、これだけのコレクションが集まる展示会は、次いつ見られるかわからないわけで、意を決して並ぶこと1時間。やー、並んだ甲斐がありました。かなり良かった。展示物はもちろんだけど、展示数も、順序やライティングの感じも丁度良いぐらい。人がいっぱいなので落ち着いて見られないのではないかという心配もあったけれど、混んでいたものの、けっこう自由に1つ1つの作品をじっくり愉しめた。
僕は陶磁器に詳しいわけではないけれど、リーの作品には、それを触ってみたくなる、持ってみたくなる何かがある。
例えば、彼女の代表的な釉薬の1つ「溶岩釉」の作品なんかは、ほんとに見てるだけで、その手触りや感触が伝わってくる。ざわざわって生理的に働きかけてくる感じだ。
なんとなくだけれど、彼女の作品には、何かしらの不安定さみたいなものがある。フリーハンドによる掻き落とでの揺らぎを持った線や、そこから発展した螺旋文や鎬文(「しのぎもん」って読むらしいが、美術館で僕は読めなかった。)が描かれる作品。そして器自体が持つ歪みなどもそうだけれど、それらは、決して「完璧」でもなければ「確実」なものでもない。どちらかというと「隙」とか「余地」みたいなものが残されてる。でも、そういった隙とか余地みたいなものが、むしろその作品の一回性を際立ててるようにも思える。いろいろな偶然や奇跡が起きて、こんな作品ができあがりました、みたいな、そんな喜びみたいなものを感じた。