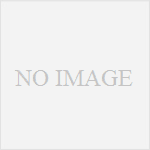天安門事件によってラストシーンが失われてしまった名作「北京的西瓜」
 なぜか思い立って大林宣彦監督の「北京的西瓜」を借りてきた。1989年公開当時は、37秒間の空白場面の挿入などで話題になった作品だ。当時ボクは高校生だったが、キネマ旬報を愛読し、アルバイトをしては映画を観に行くということを繰り返していた。当時、観たのは確かなのだが、実はその内容はほとんど忘れてしまっていた。
なぜか思い立って大林宣彦監督の「北京的西瓜」を借りてきた。1989年公開当時は、37秒間の空白場面の挿入などで話題になった作品だ。当時ボクは高校生だったが、キネマ旬報を愛読し、アルバイトをしては映画を観に行くということを繰り返していた。当時、観たのは確かなのだが、実はその内容はほとんど忘れてしまっていた。
ストーリーは、私財を投げ打って中国人留学生たちをサポートした船橋にある八百屋さんの話。実話がベースとなっているらしい。八百屋の主人を演じるのはベンガル、その奥さんがもたいまさこ。この二人がほんとにうまい。自分で駄目だとわかりながら自省が効かず、どんどん中国人留学生たちの支援にのめり込んでいってしまうお父さんの苛立ちや、そのお父さんに苛立ち、またふと自分は一体何なのだと疑問に思う妻。微妙な心の揺らぎみたいなものの表現が絶妙なのだ。
この映画には何度も「集団」が登場する。そして「集団」が登場するとき、カメラはいつもどこかの対象に立ち入るのではなく、少し引き気味に、ただその集団の様子をあるがままに捉える。映画の冒頭では八百屋内からの固定カメラで、八百屋に立ち寄る人々、値段交渉をする人、前を行き過ぎる人々、行き交う車やトラックなどが、一見無造作に捉えられる。画面の隅々で色々な声やシーンが展開されていく。その後も、人々が集まるシーンにおいて、繰り返し同じようにポリフォニックな画面作りが行われている。町内の親父たちが集う居酒屋のカウンターや、あるいは夏祭りの後の集まりだろうか、近所の人たちが集う宴会シーン、さらには中国人留学生たちも参加してるお正月の光景。カメラは同時発生的に起きる人々の会話や造作をそのまま捉える。どこかを前景化したりフォーカスするのではなく、登場する人それぞれで、それぞれの時間が流れていくのを、ありのままに捉えるのだ。これがこの映画の一つのリアリティを醸成している。
一方で、こういったポリフォニックな画面作りとの対比も相まって、人物たちにカメラが寄り添う時、それはその登場人物の心情や内面をより一層ドラマチックなものへとする。夫が中国人留学生の女性に熱を上げているのではないかと、知り合いに注意された妻は、自分が女性であることを再確認するかのように、鏡に向かい合い、徐にフェイスクリームのようなものを顔に塗り始める。このシーンは極めてドラマチックだ。妻を画面いっぱい捉え、静寂の中でシーンは進むが、「日常」の賑やかさ、騒がしさとの対比からか、何の音が響かなくても、どんな編集技工が駆使されずとも、非常に感動的なシーンとなっているのだ。
映画のラストは、本来、北京で撮影されるはずだったが、天安門事件によって中止され、日本での撮影を余儀なくされた。中国人留学生たちと、「お父さん」「お母さん」との再会シーンや、帰りの飛行機の中での感動的なプレゼントのシーンなどは、すべて日本国内のスタジオで撮影された。映画的には、おそらくセットであってもそれほど違和感なく作れていたのかもしれないが、大林監督はあえて、出演者にその事情を語らせ、そしてそれがセットであることを暴露し、感動的なシーンになるはずのところを、あえて「感動的なシーン」を作っているその舞台裏も含めて映画にしてしまった。そう、突然のメタ映画化。そこまで映画が保っていた緊張感やリアリティが台無しになってしまうような強引さだが、監督としてはそうせざるを得なかったのだろう。事実に基づき、リアリティを追求した映画だからこそ、その不合理な現実に屈服してしまったことを、映画に盛り込むことが、唯一の表現者としての抵抗だったのではないか。