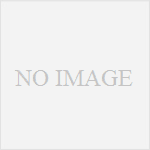古き良き時代の西部劇「トゥルー・グリット」
 日曜日にコーエン兄弟の「トゥルー・グリット」を観てきた。コーエン兄弟といえば、ついこないだも「シリアスマン」を観たばかりだが、もう新作だ。しかも、この映画もまたまた傑作なのだ。
日曜日にコーエン兄弟の「トゥルー・グリット」を観てきた。コーエン兄弟といえば、ついこないだも「シリアスマン」を観たばかりだが、もう新作だ。しかも、この映画もまたまた傑作なのだ。
「シリアスマン」を観て、この映画を観ると、ほんとにコーエン兄弟の幅の広さみたいなものを思い知る。もちろん、これまでの彼らの映画も、「ノーカントリー」やら「ファーゴ」といったサスペンス、スリラー的要素を持ったものから、「ビッグ・リボウスキ」や「オー・ブラザー」「赤ちゃん泥棒」のようなコミカル・シニカル路線、ありは「ミラーズ・クロッシング」のように古き良きフィルム・ノワール的世界へのオマージュを全面に打ち出したものまで、実に実に幅広い作品を手がけてきているので、別に驚きでもないのだけれど、今回は「シリアスマン」という最近のコーエン兄弟の作品の中でもとりわけ異色というかちょっと奇妙な映画と、そんなに時間が開いてないということもあって、そのギャップがより一層大きく感じたのかもしれない。
今回の作品は西部劇だ。しかもリメーク。残念ながら、ボクは元の作品を知らないので、リメークとしてどうなのかということはわからない。なので純粋に今、この時代に作られた西部劇という視点で見ることにはなるけれど、やっぱり面白い。どこにも無駄がなく、実にきちんと精緻に作られた、作りこまれていて、職人技という感じだ。全編を通じて男臭いかっこ良さがにじみ出ている。
ストーリーとしては単純で、父を殺された14歳の少女マティが、町のお尋ね者的な保安官を雇い、父の復讐に旅立つというもので、そこに少女の成長や、保安官との友情があるというよくあるお話だ。この先、ストーリーのネタバレが含まれているので、そういうことを気にするかたはお気をつけて。もちろん、ストーリーを知ったところで、この映画の面白さが損なわれることはほとんどないのだけれど。
この時代のアメリカでは、生きることも死ぬことも、そんなに遠くないところで共存していたのだろう。映画冒頭で、いきなり絞首刑執行とそれを物見遊山的に見守る群衆のシーンが描かれるが、そのシーンは実にあっさりとしたものだ。そう、死などはごくごく日常的なものだったのだ。映画全編を通じて、多くの死が描かれ、殺し合いが行われるが、それが大げさなものにならないのは、映画冒頭からこんな風に世界の倫理やルールが明確に示されるからだろう。マティと保安官コグバーンはチェイニーを追いかける旅の途中でいくつもの死に遭遇する。木に吊るされた遺体。その遺体を馬の背に乗せて取引に向かう男、銃撃戦によって殺され吹雪舞いちる野外に置き去りにされる死体たち、そして対決によって荒野に伏した死体。死はいたるところに存在した。人々は自らの信念や情熱やプライドを賭けて死をも厭わない戦いに挑む。
しかし、だからといって、人々にとって死が恐怖でないことはない。死の意味を十分に知っているからこそ、毒蛇に噛まれたマティを生かすため馬も男も自らの命を振り絞るのだ。ボクはこの最後の見せ場のところでは、見せ場とわかりながら涙しそうになった。人を殺すことをなんとも思わない男が、一人の少女の命を懸命に救おうとする姿は観る人の胸をきっと打つはずだ。ベタすぎる設定、古典的な展開だけど、それでもいいのだ。かっこいいし、清々しい気持ちになれるのだから。