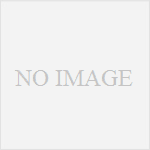織田作之助と坂口安吾の将棋を題材にした随筆
タイ、台湾の旅行から帰ってきた。旅行のことはまた別で書くとして、帰ってきて読んだ作品の読書メモ。
織田作之助はあまり熱心に読んだことはなかったのだけれど、今回、青空文庫でいくつかの作品を読んでみた。
この二編は小説というよりは随筆だろうか。浪速の棋士、坂田三吉の南禅寺での復帰戦を扱ったものだ。(坂田三吉の正式名称は、阪田三吉のようだけれど、ここでは本作の中での表記通り「坂田」としている。)
何年もの沈黙を破り、公の前に帰ってきた坂田は、名人(の弟子)である木村義雄とのこの大一番に、後手でありながら、一手損を覚悟の「9四歩(阪田の端歩突き)」を敢行する。この姿に織田は、坂田の不器用な生き方やそうせざるをえない彼が抱えて宿命みたいなものに、自身の姿を重ねる。
変わった将棋は坂田にとつてはもう殆ど宿命的なものだつた。将棋に熱中した余り、学校で習った字は全部忘れて、一生無学文盲で通して来た。(略)
〜それ故古今の棋譜を読んでそれに学ぶということが出来ない。おまけに師匠というものがなかつたので、自分ひとりで頭を絞った将棋を考へだすより仕様がなかつたのだ。自然、自分の才能、個性だけを頼りにし、その独自の道を一筋に貫いて、船の舳をもつてぐるりとひつくり返すような我流の将棋をつくるようになつた。無学、無師匠の上に、個性が強すぎたのだ。
人生のすべてを将棋にかけた坂田の姿。不格好ながらもどこまでも我流を貫いた彼の生き様に、織田は、病身、孤独で、全青春に背を向けながらも、もっとうまく生きられたのではないかというような後悔や焦燥に駆られている自分自身を見たのだ。そして勇気付けられたに違いない。なにせ坂田は、この大試合で致命的な一手で敗れたにも関わらず、次の花田長太郎の試合でも今度は1四歩という南禅寺の時とは真逆にある端歩をついたのだから。そう、多くの人は「9四歩」を無駄な一手と評し、この無駄を敗因として分析したが、坂田は自身を貫いたこの一手で負けたとは心の底から思っていなかったのだ。このエッセイの最後を締めくくる、このエピソードが坂田の坂田らしさをより強調する。彼が反省して次の試合に定跡通りの将棋を指したなら、それは彼が彼自身の人生をある種否定したことになってしまう。でも、彼はどこまでも自分を貫き通した。それは単なる天邪鬼というような言葉で片付けられるものではない。
■「散る日本」
同じ時代の同じような題材を扱った坂口安吾の「散る日本」も併せて読んでみた。(この作品の初出は1947年。織田作之助の「聴雨」は1943年だ。)こちらは木村義雄名人が名人の座から滑り落ちようとしてるその瞬間を切り取り描いたものだ。
安吾は、勝負に執念を燃やし「勝つためには全霊をあげて、盤上をのたくりまはるような勝負に殉ずる「憑かれ者」であった、木村名人が、いよいよ名人から落ちる段になって「名人としての風格」や「美しさ」みたいな精神的なところを重視し、勝つことへの拘りを捨てようとしてる様子を痛烈に批判する。それを安吾は「負ける性格」と言う。勝負師が勝負に賭ける闘魂を失ったことがただ一つの敗因だと断言する。
最終的には、この随筆は「日本」という国の精神的な脆弱性みたいなところの批判にたどり着くのだけれど、実は安吾が言おうとしてることは、最初の方にあって、それはやはり自身の生き方や価値観だったのだろう。
文学の仕事などといふものが、やつぱりさういう非常識なもので、いはばそれに憑かれているからの世界であらう。芸ごとはみんなそうで、書きまくつて死ぬとか、唄いまくつて、踊りまくつて、死ぬとか、根はどつかと尻をまくつて宿命の上へあぐらをかいている奴のことだ。
俺の芸は見世物ぢやないとか、名も金もいらない、純粋神聖、さういうチャチな根性ぢや話にならない。人様がどう見てくれようと、根は全然そつちを突き放しているから、甘んじて人様のオモチャになつて、頭を叩かれようとバカにされようとエロ作家なんでもよろしい、一人芝居、憑かれて踊つてオサラバ、本当の芸人なら生き方の原則はこれだけだ。我がまま勝手、自分だけのために、自分のやりたいことをやりとげるだけなのだから。
安吾はあらゆるジャンルの文学を書きまくって死んだ。ここで自身が書いた主張を貫き通したとも言えるだろう。その意味では安吾も坂田三吉に似てるのかもしれない。もちろん、安吾は「阪田の端歩突き」を批判するだろう。どんなに不格好だろうが卑怯もの扱いされようが、美学などというようなものから遠ざかろうが「勝つ」ことへの拘りや執念こそが「勝負師」が持たねばならないものだろうと主張するに違いない。
安吾の美学は確かに格好いい。ある種の「反美学」の「美学」なのだろうが、でも、彼は自身のこの拘りや美学に固執したあまりに精神衰弱に見舞われたのではないか。薬に頼り肉体をボロボロにしていったのではないか。そう思うと少し寂しい気分にもなるけれども、その不器用さもまたすべて安吾の安吾らしさなんだろうと思う。