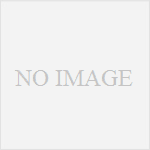顧客ロイヤルティを知る「究極の質問」

「その数学が戦略を決める」は、今日大規模なデータが簡単に集まるようになり、またその大規模なデータを解析できるコンピューター環境が整ってきたおかげで、今まで人でなければ不可能と考えられていた「決断」や「判断」や「評価」の領域にコンピューター(本書では「絶対計算」というような言葉で表現されているが)が侵食してきている様を描き出した非常に面白い本だ。「絶対計算」対「人間」では、ほとんどの場合「人間」が負けてしまうという事例を様々な分野にわたって説明している。
本書の冒頭に「ワインの値段の予測」に関する話が出てくる。
通常ワインの評価は、専門家や評論家たちが「ワインを口にふくんで吐き出す」というような方法をとる。よく見る光景だ。「今年のボルドーのワインは最高の出来」とか「今年のボジョレー・ヌーボーは10年に1度の出来だ」みたいなことを囁くのは、そういった専門家たちが、実際にテイスティングして判断している。
ここにオーリーという人物が登場する。彼は数字を分析してボルドーワインの品質を評価した。ワインの古典的な感覚的な評価方法ではなく、ある生産年の特徴がワイン競売価格の高低にどう影響するかの相関性を統計的に分析した。
彼が導き出したワインの価格を決定づける方程式は極めて単純な前提から説明できた。それは、
「収穫時期に雨が少なく、夏の平均気温が高かった年に最高のワインができる。」というものだ。そして、この前提は次のような式で表現できると導き出した。
ワインの質=12.145+0.0017×冬の降雨+0.0614×育成期平均気温-0.00386×収穫期降雨
ワインの批評家や専門家はこのような単純な式で、ワインの評価ができることを鼻から信じずバカにした。けれど、オーリーはこの式で収穫前のワインの値段や評価を予測し、見事にそれらを的中し続けた。

似たような話は、「マネー・ボール」( papativa.jp – マネーボール)という本の中にも出てきた。
この本は、アメリカ大リーグの弱小チームだったアスレチックスが常勝チームに変わっていくまでの過程を描いたものだが、いわゆるありがちなお涙頂戴的な熱血青春要素はほとんどない。アスレチックスが常勝チームに変わることができたのは、球団のGMであったビリー・ビーンが生み出した方程式「得点数=(安打数×四球数)×塁打数÷(打数+四球数)」にあった。
これはチームの得点力を求める方程式だ。自身のブログにも書いたとおり、「この公式を使うとメジャーチームのほとんどの得点が正確に予測できてしまう」のだ。そして、重要なのは、「この公式にはチーム打率や盗塁数などが入ってない。つまり、打率や盗塁数は得点を生み出すことにたいして重要ではない」ということ。
この方程式の理論に則って考えると、例えば、足の速い盗塁ができる選手よりも、選球眼の良い四球が多い選手のほうが重要ということになる。実際、この理論に沿ってチームの改革を進めていき、アスレチックスは万年Bクラスチームから、常にAクラスで優勝を争うチームに生まれ変わったのだ。
これらの話は、非常に複雑に思えるものや、数量化や方程式化するのが難しいだろうと考えているものが、意外と単純な要素で簡単な方式で推量することができることを明らかにしている。
その意味では、この「顧客ロイヤルティを知る「究極の質問」 (HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS) 」という本も同じようなことを明らかにしたと言えるかもしれない。

この本を知ったのは、最近になってようやく「グランズウェル ソーシャルテクノロジーによる企業戦略 (Harvard Business School Press) (ハードカバー)」を読んだからだ。買ったのは随分と前のことで、ざっとは読んだのだけど、途中で放置してた。なんだかふと思い立って手にして読んだら、うーん、なんでこれをちゃんと読んでなかったのかとすごく後悔したのだけど、まぁ、それはいいとして、本書の中に、この本が紹介されていたのだ。それもここ数年で発売されたビジネス書の中でも最も重要な本のうちの1つだと絶賛されていた。(「グランズウェル」についてはこれはこれで別途エントリーにまとめようと思う。)
「顧客ロイヤリティ」を測定するための単純な質問は、つい最近読んだ、「顧客の信頼を勝ちとる18の法則-アドボカシー・マーケティング-」(papativa.jp – 顧客の信頼を勝ちとる18の法則-アドボカシー・マーケティング)でも紹介されていて、ブログにも書いたところだった。なんとなくここには偶然の導きがあるなと感じたので読んでみたのだが、ほんとに素晴らしい本だった。少なくとも経営者は読んでおいたほうが良いだろう。
「顧客ロイヤリティ」というものも、重要であることは誰もが理解しているに違いないだろうけれど、実際、じゃぁ顧客ロイヤリティをどの測定したらいいのかということへの回答は誰も持っていなかったというのが現状ではないだろうか。さらに、顧客ロイヤリティが収益力や成長性や売上といったものと相関性を持ってることを証明することも難しいことは言うまでもないし、また、仮に、複雑なアンケートや調査を行って「顧客ロイヤリティ」を導き出すことができたとしても、それを導き出すための変数があまりにも多く複雑だと、その結果をもって顧客ロイヤリティをどのように育成していけばいいのか、獲得していけばいいのかというフィードバックがそもそも出来ないという問題もあったわけだ。
そこで本書の考え方が登場する。タイトル通りこの質問はまさに「究極の質問」だ。長年、顧客ロイヤリティを様々な角度から調査したり評価しようと考えてきた専門家や企業幹部から見たら、拍子抜けするぐらいに単純化されている。
その質問とは、「X社を友人や同僚に薦める可能性は、どのくらいありますか?」と訊くだけだ。
(X社のところは「製品名」とか「サービス名」とか、顧客ロイヤリティを測定したい対象名を入れれば良いだろう)
これに10点満点で何点かを回答してもらう。
10点は薦める「可能性が非常に高い」
5点はどちらでもない
0点は「可能性が非常に低い」
直感的に何点かをつけてもらえば良い。回答結果は3つのセグメントに分けられる。
10点、9点をつけた顧客は、「推奨者」
8点、7点をつけた顧客は、「中立者」
6点以下は「批判者」
となる。
(ただし、欧米では10点満点で10点、9点がAAやAを表すということや、6点以下がダメというのは誰もが理解していることかもしれないが、日本には残念ながらそういう文化はないので、ここには少し工夫は必要かもしれない。日本では5段階評価のほうが馴染むかもしれないし、あるいは10段階評価にしてもその裏側についての説明が必要かもしれない)
推奨者は、その会社やサービスへの満足度が高い。このセグメントはたいていの場合、再購入率が高く、顧客維持率も高い。そして、紹介客の80%は、このセグメントの客に薦められている。
中立者は、「受身」で満足しいている状態。ロイヤリティではなく、惰性が動機づけになってる場合が多い。
批判者は、その名の通り。否定的なクチコミの大部分は、このセグメントから発せられる。
そして、ここでも以下のようなシンプルな計算式が登場する。
推奨者の割合 – 批判者の割合 = 推奨者の正味スコア(NSP)
このNSPが収益性や売上などと相関性を持つ指標となる。
いろいろ事例が出てるので、本を読んでもらえればわかるが、平均的にはNSPが12%ポイント増加すると、企業の成長率が倍増するとある。
また、NSPは、ほぼどんな業界にでも使える指標でということを、膨大な調査とサンプル収集、分析によっても明らかにしている。(一部、一部のプレイヤーでの支配性が高い市場や、そもそもその市場において顧客が他に選択肢を持てないような領域においては該当しないケースもある。)
企業はこのNSPスコアを定期的に測定して、このスコアをあげることを目標にすることで、「顧客ロイヤリティ」という裏付けを伴った、売上や利益などの評価ができるわけだ。
顧客ロイヤリティを「推奨意向性」だけで測定し、さらにそれを推奨者と批判者の割合からNSPという指標を出す。
この単純さがいいのは、顧客ロイヤリティを伸ばすのは、とにかく自社や自社サービス、商品を他者(社)に薦めてもらえるようにしなければならない、という実際の企業行動や活動に繋がりやすいということがあるだろう。
複雑な計算式で導きだされていたら、何を重視したらいいのか、どこをどうすれば改善できるのかが直感的にわからない。
推奨意向者を増やす/批判者を減らす、というのはとにかくわかりやすい。わかりやすいということは行動に繋がりやすいということだ。
数値化するということもすごく重要なことで、たいていの場合、数値として表せないものは改善していくのは難しい。
NSPのような指標があるから、いかにして推奨者を増やすかと、いかにして批判者を減らすかということに意識が向くわけで、これがただ掛け声として「顧客ロイヤリティを高めよう!」だけでは、なかなか実際のところ顧客ロイヤリティを高めることはできない。そもそも高まってるかどうかの判断もできない。
少し話は脱線するが、うちの会社では労働時間の長さというのが常々問題になっていた。
それは今も解決したというわけではないけれど、でも改善に取り組みだしてからと比較すると、実際、今はものすごく改善されていたりする。
この問題に取り組みだしたのは今から4年前で、それまでは勤務時間とか労働時間は、もちろん測ってはいるけど、それをちゃんと意識して見たことはなかった。なんとなく感覚的に今月は稼働が高いなとか、帰りが遅いなとか、あのチームは高稼働が続いてるなというようなことを見てるだけだった。
ある出来事の後から、勤務時間や労働時間を事務所やチームなどで細かく見るようになった。事業経営会議でもその数値は報告されるし、役員には強制的にデータが毎月集計されて送られてくる。
そうすると人はそれについて意識する。意識するというのは重要なことで、数値が悪いとなると、改善していかないとという思考が働く。短期的にすぐに変わるかというとなかなかそういうわけにもいかないのだけれど、それでも意識しているか、意識して行動しているかで、結果は随分変わってくる。
意識しだしてからの実際の数値は、かなり改善されてきてるのは事実だ。
このブログを読んでる人の多くは、うちの社員で、社員からしてみたら、まだまだ全然だよという人も多いとは思うけれど、それでも4年前に較べるとものすごい改善されている。(まぁ、このあたりのことは「感覚的」「精神的」なところも大きく影響を及ぼすだろうから、数値はそうでも感覚的には違うよ、という声があるだろうとも思う。)
今の状態がベストだとも思ってないし、まだまだ改善の余地はあるわけだけど、数値化して意識することや、その数値がどう推移しているかを見て、状態が良くなってるのか悪くなってるのかを把握するということは、そもそも「改善」に取り組んでいくということにとって、すごく重要なことだということを言いたかっただけだ。
さて、本書には、この質問を活かしていくためのヒントや、気をつけないといけないことなどが色々説明されている。
質問はすごく単純だけれど、単純であるがゆえに、使い方を誤ると、全然意味のないものになってしまうので、それは本書を読んで注意をしてもらいたい。
僕はこの本を読んで、この質問は、顧客に対して利用できるのはもちろんだけど、他にも応用できる要素がたくさんあるなと考えた。1つは「従業員」に対してだ。従業員の会社にたしての満足度や評価みたいなものにも応用できるのではないか。
最近は、従業員へのマーケティングみたいなことも話題にあがる。どうやって従業員のモチベーションを高めるのかとか、それを専門に調査したりコンサルティングしたりする会社もあるぐらいだ。
そういった会社の調査や分析はそれはそれで無意味なものではないと思うけれど、実は、従業員の満足度だって、この質問やNSPでほぼ把握できるのではないか。もちろん、誰がどんな回答をしたかということが分かってしまうと、それがバイアスになってきちんとした評価ができなくなるという点は、従業員の場合にはよりシビアだろうけれど、そのへんをうまくカバーできれば、「推奨意向」と会社への満足度とか、ロイヤリティは近しいものになるのではないだろうか。
そして、これはどうだかわからないけど、会社へのロイヤリティが高い従業員が増えれば増えるほど、企業としての競争力も高まるのではないかとも思う。(が、もちろん、単に会社への満足度が高いだけではだめで、その前提として、その会社が顧客に対しても高い満足度を与えられているということは必要。そうしないと、従業員にとっては居心地いいけど、顧客から見たら、ダメな会社みたいになることだって十分考えられる)
経営者は顧客ロイヤリティを高めるということももちろんだけれど、自社を他者(社)に熱狂的に推奨してくれるような従業員をつくっていくことも仕事の1つなのではないか。そのための環境や制度やルールやポリシーや理念、仕事のあり方やサービスの内容、どのような顧客と付き合うか、といったことを考えていかなければならないのではないか。なんとなくだけどそんな風なことを考えていて、本書の「質問」が従業員の満足度を考えるヒントになった。
あと、ECサイトなどでのサイト運営などでPDCAサイクルを回していく際にも、単純にセッション数だとか、カート放棄率や、コンバージョン率みたいなアクセス解析数値だけではなく、こういう指標もKPIとして設定していく必要もあるかもしれない。(となると、末端顧客から評価を収集して、分析するという仕事が必要になる。) NSPと収益性が連携していることは、本書で十分に示されているので、このKPIを高めることは、すなわちゴール=たいていの場合は売上最大化とか利益とか?をもたらすことに直結していくだろうし。経営者にはオススメと書いたけれども、こういうところにも応用は十分可能だと思うので、現場の人でも一読する価値はあると思う。