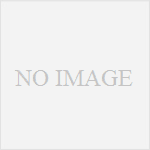志賀直哉「焚火」
いつもは最近読んだ本や手にした本の備忘録として本を紹介しているのだけれど、ちょっと趣向を変えて、とにかく自分が好きで、好きで、もっと皆に読まれて欲しい本を紹介する。手軽さも加味して、まずはいくつかの短編小説を紹介しようと思う。最初は王道、ド直球で行く。志賀直哉だ。
志賀直哉の文章はすごく簡潔だ。
一時期、ボクは彼のような文章にすごく憧れを抱いていた。ボクはどんな文章でも過剰に言葉を並べ、回り道を何度も繰り返し、自分自身でさえも、冗長だなぁと思うような文章を書いてしまう。それが癖だ。いつも何か足りないと思ってしまうのだ。自分の文章と志賀直哉の文章を較べるというのも恐れ多いけれども、しかし、志賀直哉の文章は、過剰さや冗長さとは正反対にある。志賀直哉の文章は、削って削って、もうこれ以上削りようがないところまで削ってということを突き詰めていったような文章だ。それ以上踏み込めば、それは言葉の圧倒的な密度を目指す「詩」になってしまいかねない。それでも志賀直哉の文章は詩にはならず、良い意味で散文が持つ、余裕というか、付け入る隙というか、そういうものを兼ね備えている。言葉は少ないのに圧倒的にクリアでリアリティに満たされた描写なのだ。
なので、志賀直哉の小説は筋書きや内容は覚えてなくとも、各作品のシーンごとの情景だけが強烈に頭にこびり付いていたりする。志賀直哉の志賀直哉らしさが最も発揮されるのは、ボクは数々の短編群だと思ってる。「暗夜行路」みたいな長編も、嫌いではないのだけれど、やはり彼の短編が持つ独特の言葉の緊張度みたいなものは、他に代わるものがない。
 志賀直哉の短編には他にも色々好きなものがあるけれど、1つ選ぶならこの「焚火」という短編を選ぶ。芥川龍之介は志賀直哉の文書がひどく気に入っていたけれども、「小説中、最も詩に近い小説」として、この作品の名前を挙げている。(「文芸的な、余りに文芸的な」)
志賀直哉の短編には他にも色々好きなものがあるけれど、1つ選ぶならこの「焚火」という短編を選ぶ。芥川龍之介は志賀直哉の文書がひどく気に入っていたけれども、「小説中、最も詩に近い小説」として、この作品の名前を挙げている。(「文芸的な、余りに文芸的な」)
手元に作品がないので、細かいところはうろ覚えだけれども、それでもこの作品で描かれた情景は、今でもボクに痛烈なイメージを残している。ボクにとっての、深い森、静かな湖。そして焚火。これらのイメージは、ほとんどこの作品から得られているのかもしれない。高校時代、登山部だったボクは、この作品で描かれたような環境に身を置き、同じように焚火を囲んで、仲間の話を聞いたりしたことが何度かある。その時の情景を思い浮かべようとすると、いつもこの「焚火」を読んだ時に思い浮かべたような、湖畔や森の情景が浮かび上がってくる。この小説の最後の燃え残った薪を湖に投げるイメージ、火の粉がぱっと舞いながら、緩やかにスローモーションフィルムを見てるかのように薪が弧を描き湖に落ちて行く。そして、湖と森に再び静寂が訪れる。このパートのイメージは、ボクの「湖畔」や「焚火」のイコンのような存在になってしまっているのだ。
小説にはそういう力がある。世界を再構成する力だ。その文章を読んで、イメージした世界や状況によって、今まで見ていたものや感じていたものが、別の意味や輝きや不思議さを持って立ち現れてきたりする。今まで意識してなかった物事が、急に目につくようになったり、面白く感じられたり。それが言葉の力だし、読書という体験を経ることの効果だ。これは読書しない人、小説を読まない人にはなかなか理解しにくい感覚だと思う。ストーリー小説が大好きで、あまりこの手のストーリーらしきものがない小説がよくわからないという人に、ぜひ読んでもらいたい作品だ。すごく短いので気軽に読めるし、何度でも読み返せる。そして、読めば読むほどに、その行間とか言葉の使い方、置き方、それらすべての技法から浮かび上がってくる美しい描写・風景といったものが、そういうものだけで「面白い」ものであり、それ自体で十分味わえ、愉しめるものだということに気づくだろう。