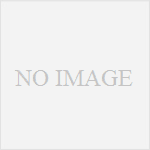グルスキー展、のようなもの。
グルスキー展を観てきた。素晴らしかった。

グルスキーの写真はウェブなどで見てたレベルだったけれども、実際のあの巨大なサイズの写真の前に立つと、もう、それはまったく違う、別の何かのようにさえ思えた。
グルスキーの写真の多くはとにかくオブジェクトが多い。画面の隅々までなんらかのオブジェクトが凝縮して配置される。被写界深度は限りなく深い。でも、張り詰めた緊張感みたいなものは感じない。かと言ってニューカラー派のような「意味」という呪縛からの解放だとか、「決定的瞬間との決別」といった意気込みも感じられない。なんとも言えない微妙なバランスの上に成立している。
グルスキーの写真の面白さは、その殆どの作品が、人々の営みだとか、経済活動だとか、それぞれの勝手な意図しない活動の結果や集約が、ある種の調和を偶然作り出してしまうところにある。その光景は実はいたるところにあるのだが、僕らのレアな視界や視線では、それを物理的に捉えることができなかったりする。グルスキーはそれをテクノロジーによって成し遂げる。
パリの集合住宅を正面から?極めてフラットを切り取った「パリ、モンパルナス」。遠目に見ると、モンドリアン風の抽象画のようにも見えるけれども、きちんと見れば、一つの一つの細かな「四角形」に、人々の営みが映し出される。この集合住宅に暮らす人たちは、連携して何かに取り組んでるわけでもないのに、各々の暮らしの結果は、調和をもたらす。僕らはその「結果」を美しく感じる。
色々なメーカーが少しでも消費者の興味を惹きつけようと努力してきた結果、色彩豊かなグラデーションとパースペクティブが構成された「99セント」。どこにでもあるスーパーマーケットや100円ショップが、まったく別の何かに変容する。

そう。グルスキーの写真は、現実と、それとは別の何かとの間を行き来する。リアルと抽象の間を。
油やゴミの浮く汚い河の水面の揺らぎはアクションペインティングのキャンバスのようでもあるし、巨大な案内ボードが画面上部を占める「フランクフルト」は、空港ではなく、何かのタイポグラフィを見てるかの錯覚に陥る。
しかし、これらはすべてあくまでも何らかの活動の結果、偶然に組織されたものだ。だから、グルスキーは必ずといっていいほど、キャンバスの中に現実(リアル)の手がかりが配置する。それがなければ、単に「面白い写真」になってしまうからだ。
「フランクフルト」にしても、抽象化ということだけを考えるなら、画面下部の人々はいらないかもしれない。有名な「カミオカンデ」にしても、「大聖堂」にしても、画面右隅に人が配置されることで、そのオブジェクトの巨大さがより際立つのと同時に、中心のオブジェクトの抽象化にはあえて逆う。
あるオブジェクトの前に立つ人たちによって、写真の中でそのオブジェクトは一旦括弧に入れられる。オブジェクトに対峙する人々と、その構図をさらにその外側から見る私たち。キャンバスのオブジェクトは巧妙に二重化される。これによって、オブジェクトには、滑稽さや、諧謔性のようなものが帯びる。
グルスキーの写真を見て、難解な現代アート作品というよりも、少しおかしみを醸し出す、批評性を感じるのは、グルスキーのこういう仕掛けに秘密があるのかもしれない。
「無題Ⅵ」と冠されたジャクソン・ポロックのアクションペインティングの絵画作品を、そのまま写真に納めた作品がある。
対象物そのものは、何億という価値のある絵画であり、抽象であり、「何物でもない何か」なわけだが、それをそのまま写真におさめ、その写真が現代アートとして美術館や博物館に展示される。
この構造そのものが、「アート」を相対化する。アンドレ・ブルトン的な批評性というか。
グルスキー作品を「美しい」と感じたり、そこに「調和」を見出してしまうような認識のあり方とか感覚そのものが、ある種、アート世界によって組織化されたものなのではないか、グルスキー作品は、そういった問題意識も突きつける。
ただ、この手のコンセプチャルなものが、コンセプチャルなものであるが故に、作品そのものは面白くもなんともなかったり、評価しようのないものだったりするものが多い中、グルスキーの写真は、写真そのものも極めて高い作品性を持っていて、見ているだけで、十分に愉しくワクワクさせてくれるものがある。