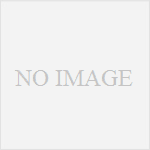ブラック・スワン―不確実性とリスクの本質
 「ブラック・スワン[上]―不確実性とリスクの本質」「ブラック・スワン[下]―不確実性とリスクの本質」─ 読んだのは去年の夏ぐらいだけれど、ひじょーに面白いのでまとめておこうと思う。これは世界の見方や考え方を変える力がある本だと思うので、ぜひ一読をオススメする。
「ブラック・スワン[上]―不確実性とリスクの本質」「ブラック・スワン[下]―不確実性とリスクの本質」─ 読んだのは去年の夏ぐらいだけれど、ひじょーに面白いのでまとめておこうと思う。これは世界の見方や考え方を変える力がある本だと思うので、ぜひ一読をオススメする。
著者はこの世の中を「月並みの国」と「果ての国」のものとに区別する。経済学者や社会学者たち、哲学者や数学者たちの多くが未だにこの「月並みの国」と「果ての国」を混在してしまっている。そこに大きな間違いがあるのだと指摘する。
月並みの国と果ての国
月並みの国では、「特定の事象が単独で全体の大きな部分を占めることはない」。
言わば、偏差値やガウス分布といった平均値から事象を捉えることに意味のある世界だ。著者は月並みの国の例として、例えば、人間の体重や身長、カロリー摂取量などをあげる。これらは、そのサンプルの中でどれだけ特異な値をもった人がいたとしても、その特異値が全体に与える影響はごくわずかしかない。「平均」には大きな影響を与えないのだ。
一方で、果ての国。
例えば、「財産」。無作為に抽出した人を1000人集める。その中に地球上で最も財産がある人物を一人加える。身長や体重やカロリー摂取量では、どれだけ飛び抜けた値を持った人を加えようが全体への影響はわずかだったが、財産の場合はどうか。たった1人の大金持ちの財産には、その他999人の全財産を集めようが届かない。1人の金持ちが99.9999% と限りなく100%に近い比率を占めてしまう。そう。果ての国とは、「たった一つのデータが集計量や全体に、圧倒的に大きな影響を及ぼ」してしまう。この世界では「平均」には意味がない。たった1つの異常値が、全体を決定してしまうからだ。
多くの人々は、この社会の事象が「果ての国」に属しているのにも関わらず、「月並みの国」で暮らしていると勘違いし、月並みの国の論理やセロリーを鵜呑みにしている。そして、たまに起きる「果ての国」の事象のことを、何百年、何万年に一回の「偶然」「たまたま」「異常値」であると片付けてしまう。
私たちはこれらの特異な事象が、いつでも起き得るような「果ての国」の住人なのだということを肝に命じておかなければならない。著者は言う。
とても稀な事象の確率は計算できない。でも、そういう事象が起こったときに私たちに及ぶ影響なら、簡単に見極められる。ある事象が起こる可能性がどれぐらいかわからなくても、その事象が起こったらどんな影響があるかはちゃんと把握できることがある。地震が起こるオッズはわからないが、起こったらサンフランシスコがどんなことになるかは想像はできる。意思決定をするときは、確率(これはわからない)よりも影響(これはわかるかもしれない)のほうに焦点を当てるべきなのだ。不確実性の本質はそこにある。
月並みの国は、平均やガウス分布といったモデルが適応されるので、私たちは過去から未来や将来を学ぼうとする。しかし、そもそも経済や世界について未来の予測が可能だろうか。過去や歴史を教訓にしたり、それらの平均や標準から何かを予期したり予想することはそもそも無意味ではないか。
私たちは起こったことから、それが起きた原因や要因を引っ張り出してきて、あたかもそれが因果として筋道が通ってるかのよう考えてしまいがちだが、それは結果から導けるものだ。その瞬間、その瞬間では、ある結果を引き起こす(かもしれない)原因や要因は無数に存在する。それらにすべて気を配り、それがどんな影響を与えるかなんて想像することはできっこない。「歴史はリバース・エンジニアリングできない」のだ。机の上に氷があるとする。この氷が1時間後に溶けて、机の上にどのような水面が形作られるかは、ある程度予想できるだろう。しかし、すでに溶けてしまって液体となった水から、1時間前にこの水がどういう状態であったかを予測することは不可能に近い。そもそも個体であったかどうかさえわからない。
私たちがよくやる間違いの一つは、固体から液体への変化を事後的にわかったつもりになって、液体がそれ以前にどうであったかということも分かるような気がしてしまう、勘違いしてしまうということだ。
本書が興味深いのは、これまでの経済理論や社会学といった従来の学問への痛烈な批判と共に、著者が言うこの「壮大な非対称性」が成り立つ「果ての国」において、どのように世界を認識し、どのように考え、行動すべきかという一種の生き方や哲学をも提唱しているところではないだろうか。「果ての国」が支配し、予期できない予想できないからこそ「予想できない」ことが起きる、この世界においての、私たちはどのような処世訓を持つべきか?
著者が提唱する戦略は、言ってみれば、未知なものは未知なまま扱い、その未知なものがどのような影響を及ぼし得るかということに従って判断せよ、というものだ。
未知なものがわかることは決してない。定義によって未知は未知だからだ。でも、そんな未知でも、自分にどんな影響を与えるかを推し量ることはできる。何かを判断するときは、そんな推量にもとづいて判断を下すべきだ。
なんとなく、著者の主張から、ボクは浅田彰の「逃走論―スキゾ・キッズの冒険」を思い出した。スキゾとパラノで言えば、本書が奨めるのは明らかにスキゾ型の生き方に近いだろう。
ただ、本書の著者はたった1つの特異な事象や異常値が、すべてを刷新したり塗り替えたり、潰したりしてしまうような「果ての国」においても、真面目にこつこつ取り込んでおくことが、セレンティピティを掴むことに繋がるのだというようなことも語ってるので、あながち、スキゾ/パラノ構図の、パラノイア型の生き方を否定しているわけではないのだろうけれど。
著者が提唱する「果ての国」での処世訓をいくつか、そのまま引用しておきたい。
●バーベル戦略
可能な限り超保守的かつ超積極的。「中ぐらいのリスク」の投資対象にお金を賭けるのではなく、お金の一部、たとえば85%〜90%をものすごく安全な資産に投資する。そして残りの10〜15%はものすごく投機的な賭けに投じる。あらん限りのレバレッジがかかった投資。一方で大きなリスクをとり、一方では一切リスクをとらない。極端なポートフォリオを組むこと。
●細かいことや局所的なことは見ない。
杓子定規になるな。運は準備を怠らないものに味方する。毎朝具体的な何かが見つかるなんて思ってはいけない。でも、必死で働かないと、まぐれには出会えない。
黒い白鳥を厳密に予測しようなんてやめたほうがいい。予期してなかった種類の黒い白鳥に振り回されやすくなる。
予測ではなく、備えのほうに資源を費やすのだ。すべてを警戒し続けるのはまったく不可能なことだ。
●チャンスやチャンスみたいに見えるものには片っ端から手を出す。
チャンスなんていうものはめったに来ない。思ってるより稀なのだ。よい方の黒い白鳥は避けて通れない第一歩なのだ。だから黒い白鳥に自分をさらしておかないといけない。
いい偶然が起こりえる世界には最大限自分をさらし、悪い偶然が起こりる世界ではあらんかぎり被害妄想みたいな態度をとる。いい偶然の世界では、損が限られてるなら、あらん限りの力を尽くして積極的に投機的に、なんなら「理不尽」にならないといけない。
〜そういうチャンスに対するエクスポージャーを最大化する。そういうことをするなら、大きな街で暮らしていることが大きな価値を持つ。運のいい出会いができるオッズが高くなるからだ。セレンディピティのまわりでウロウロしてエクスポージャーを高めることができるのである。そういう形での出会いで得られるいい不確実性は、「インターネットの時代なんだから」田舎に住んでいても十分に人とやりとりできる、なんてトンネル化した考え方では見過ごされている。
以前紹介した「たまたま―日常に潜む「偶然」を科学する – papativa.jp」と併せて読むと、さらにこの世界の「偶然」とか「たまたま」がいかにボクたちの認識を歪めてしまうか、いかにボクらが確率や統計の罠に絡め取られてしまってるかを知ることができると思う。