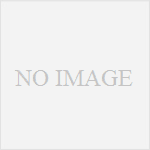映画「桐島、部活やめるってよ」はすばらしい青春映画
ずっと観たかった「桐島、部活やめるってよ」(8月11日(土)公開 映画『桐島、部活やめるってよ』公式サイト)をようやく観ることができた。

観てよかったー。これはなんともいえない感動だ。しかし、この感動をきちんと説明するのは難しい。わかりやすく胸にジーンと来るようなストレートな「感動」ではないからだ。これは、明らかに新しいタイプの青春映画なんだと思う。青春が持つ空虚さや孤独を実に巧みに描くことに成功している。観てて何度も息が詰まりそうになった。今、青春映画が成立するとすれば、こういう形でしか成立しえないのではないかと思う。
以下、完全ネタバレなのでご注意を。
この映画で徹底的に描かれているのはいろんな形の「屈折した感情」だ。
それはある種の「挫折」と言ってもいい。しかし、登場人物たちは皆、高校2年生だ。「挫折」というにはまだ早い。「挫折」を認めるには、まだまだ可能性がありすぎている。でも、登場人物達は気付いている。自分たちが何もできないこと、何ものでもないこと。それと正面から向き合うことは、彼らにとっては物凄くハードルが高いことなのだろう。だから、彼らは「桐島」に救いを求めている。桐島がいること、桐島とつるむこと、桐島と付き合うこと、桐島との関わりあいの中で、自分が何ものであるかを誤摩化して生きてる。
しかし、そのごまかしが桐島の不在によって明るみに出てくる。桐島の不在によって、自分が自分で隠蔽していた見たくなかった本当の自分の姿に気づき始める。
この映画は、金曜日から始まる。そして土日挟んで火曜日までで終わる。金曜日に生徒達には進路希望のアンケートが配られてる。これの回答は来週水曜日までとなっている。つまり、この映画の生徒達は、自身の進路についての希望を出す水曜日以前にその役目を終える。高校2年生という、人生での岐路を決める重要な決定時期の、しかも進路希望を提出の時期という、おそらく自分が何者なのか、これから自分はどうなるのかということに、本格的な不安や焦りを感じ、自我が揺さぶられる数日間を背景にしている。歳をとってから見たら、そんな数日なんてのは、もう忘れてしまうような些細なことになってしまうのかもしれないけど、多分、その時、その瞬間というのは、皆、あんともいえない不安や焦燥感にかられていたのではないだろうか。
登場人物の中でも、特に、桐島をを取り囲む所謂「リア充」連中は、汗臭い、血と涙みたいな努力を格好悪いものとして捉えている。にも関わらず、彼らは他の生徒たちよりも何でもうまくできるし、モテる。宏樹はろくに練習にも行ってない幽霊野球部員にも関わらず、キャプテンからは試合に来てくれないかと懇願されたり。頑張るとか努力とか、そういったものとは無縁に、それでも「できてしまう」うらやましい奴らがいる。
桐島の不在は、そんな「リア充」連中の歯車を狂わせる。自分たちは桐島によって満たされていただけだったのではないかということに気づき不安になる。その不安が微妙な人間関係の歪みを生み出す。桐島が映画に登場しないからこそ、それぞれの人の挫折や、その挫折をごまかそう、取り繕うとする様により一層リアリティが生まれていく。
桐島の彼女、梨紗は、彼氏が桐島であることに優越感を抱いている。なにせ桐島はバレー部のキャプテンでもあり、どうやら頭もいい。学校中の誰からも一目を置かれる存在だ。もちろん梨紗は自身の美貌やセンスにもかなりの自信を持っている。だから自分に合うのは桐島だと思っている。そんな桐島が、自分を無視して、何の相談もなしにバレー部を辞めてしまう。梨紗は、それに苛立つ。この苛立ちは、自身のアイデンティティが崩れることに対しての恐怖への抵抗だ。桐島の能力や才能や、周りからの評価を、自身のアイデンティティをつなげることで、自身の存在価値を確認していた梨紗にとって、桐島に無視されるということは、挫折以外のなにものでもない。それまで仲良くつるんでいた同性たちへの目線への過剰な反応というのも、桐島なき自分への自信のなさの現れなのだ。
宏樹は、最初こそ、何ものにも熱心になることを避けクールを装いながら、徐々に自分自身のごまかしに自覚的になっていく。
3年夏の引退時期を過ぎてもなお、練習に打ち込む野球部キャプテンの姿を見て、宏樹は「なぜ引退しないのか」と尋ねる。
キャプテンは「いちおうドラフト会議が終わるまでは」と語る。もちろん、キャプテン自身も、そして宏樹も、キャプテンにドラフトがかかるとは思ってもいないだろう。そんなことは百も承知だけれど、でもキャプテンは練習を辞めない。宏樹は、そういうキャプテンの姿を見て、逃げている自分の姿が息苦しくなる。
映画のクライマックスで、宏樹は、お金もかかり大変な8mmフィルムでの映画撮影にこだわる映画部の涼也にも、「将来は映画監督ですか?」と尋ねる。宏樹にとっては、こんな情熱を注いでるのだから、キャプテンと同じように、それが適わぬ夢だと頭では理解していても、一途の望みを持って、活動に取り組んでいるのかと期待している。しかし、涼也はあっさり「無理」と言い放つ。そして涼也は確かこんな風に言う。それでも、こうやって映画を撮ることで、自分の好きな映画の世界と繫がっていられるような気がする。
この答えを聞いて、宏樹は涙がおさえられなくなる。「桐島を待っている」ということを理由として、何かに懸命になることから避け、ただ「出来る奴は出来るし、出来ない奴は出来ない」とクールに言い放つことで、能力や才能や努力といったものなんて、最初からある程度決まってるし、そういうもんだと自分自身で納得する。それは、自分が桐島のようにはなれないという挫折感へのごまかしでもあるし、自分が挫折する恐ろしさからの逃亡でもある。そうしたごまかしや逃亡に、キャプテンの言葉と、涼也の言葉は突き刺さるのだ。
映画のラストシーンでの宏樹の号泣、そしてそれでも桐島へ電話しようとする、その姿は、かなり泣ける。
自分が宏樹ほどではないにせよ、自分が全力で力を出し切って、能力を出し切って、それでも何も成し遂げられなかった時、その時の恐さを先回りして、努力やら懸命さみたいなものから逃げてなかったろうか。自分は逃げてないだろうか。
桐島の不在がつきつける挫折は、こういった「リア充」たちだけのものではない。
桐島の属するバレー部の連中も、チームの強さが、桐島の存在そのものだったということに、桐島の不在によって気付かされることになる。桐島の代役のリベロは、自分がどれだけ練習しようが桐島にはなれないということは最初からわかっていた。桐島が実際にいなくなり、自身が代役を本当に務めなくてはならなくなった瞬間、彼は絶望に襲われる。
桐島の彼女梨紗と同じグループで、バトミントン部の実果は、そもそも自分には才能がないと思っている。自分は姉のようにうまくはなれない、姉のような才能がないと諦めている。でも、彼女は部活が好きなのだ。しかし、才能がないと自身で認めながら、部活に熱心になっている様を、同性グループには悟られたくない。だから彼女は、部活やってるのは内申書のためで、自分は別に本当に部活をやりたいわけでもない、という虚勢をはる。このあたりの細かい設定や演出も、この年頃の気持ちをすごくうまく現してる。
どれだけ頑張っても姉のようにはなれない、と分かってても、部活をやっている、だからこそ、桐島の代役として、自分が桐島を超えることは絶対不可能だということを十分に理解しながらも、それでも熱心に練習をしているリベロの気持ちが実果にはよくわかるのだ。
吹奏楽部の部長の女の子は、桐島を待つ男子連中らがバスケに興じる様を屋上から眺める。その視線の先には、宏樹がいるが、宏樹は、沙奈と付き合っている。好きだけれども、どうにもならない。でも、好きだから眺めたい。結局、部長は、宏樹と沙奈のキスを見せつけられてしまう。この絶望たるや。部長は、自分の想いをすべてふっきって清算するために、部室に駆け戻り、そして吹奏楽の演奏に打ち込む。
映画のクライマックスに向けて、この吹奏楽部の演奏が、映画バックの音楽としてクライマックスの情感を高めていくあたりの仕掛けもすごくニクい。
桐島を取り囲み、様々な人達の想いが交錯し、そして多くの人々が挫折を味わう。
しかし、それでも皆は最後まで、桐島に救いを求めてる。桐島が学校に現れたら、桐島が来ればなんとかなるのではないかと思い、桐島を追いかけ続ける。しかし、桐島は結局、最後まで姿を現さない。桐島がゴドーであることは多くの人が指摘してる通りで、もちろんゴドーがゴッドであるように、桐島はキリストのもじりには違いない。「部活やめるってよ」というのは、「復活やめるってよ」とも読み取れる。つまり、人々が救済を求めてキリストの復活を信じる。しかし、キリストは復活しない、というわけだ。
しかし、この映画の中で、映画部の連中だけは、桐島の不在などにはまったくなんの影響も受けず、ただ淡々と、自分たちが作りたいゾンビ映画をつくろとする。そう、彼らは、もう最初から自分が何者でもなく、何者にもならないということを悟っているのだ。誰からも相手にされず、こんなことを続けていても何にもならない、愛だ恋だという世界とも無縁に生きている。
映画部の顧問は、ゾンビ映画などにお前らのリアリティはないだろうと貶し、お前らのリアリティは、半径1m以内にあるだろう、というようなことをアドバイスする。学校での悩みだとか恋だとか、そういった身の周りにあるものの方がリアリティがあるだろうというわけだ。ところが、彼らにとっては、ゾンビ映画の方がよほど自分たちの青春を捧げられるものなのだ。彼らの半径1m以内には、桐島も存在しないし、愛だ恋だも存在しない、何かに悩もうとしても、周りから自分たちの存在は無視されてる。ある意味彼らの青春は死にながら生きてる/生きながら死んでいる、まさに彼らがゾンビそのものだから。
そんな彼らが、桐島を求め屋上に集まった連中たちに、自分たちの神聖な映画撮影を邪魔したことを謝れと反撃に出る。
妄想の中で映画部の連中は、桐島の取り巻き「リア充」たちを食いちぎっていく。現実には、おそらく返り討ちにあって惨めな敗戦を味わってるはずなのだが、カメラのファインダー越しには、彼らの思いは成し遂げられる。
桐島、桐島と勝手に騒ぎ立て、自分たちの挫折や悩みこそが、全てだと思い込んでいる連中たちに対して、映画部たちは、お前らは、まだそうやって桐島に頼って、桐島に自身を支えてもらわなきゃならないのかと半ば呆れてる。お前らだって、何ものでもない、桐島がいなければ、何もできない、お前らだって、俺たちと対して変わりはしない。お前らだって桐島がいなければゾンビとして生きていくんだ、映画部の連中たちは、そんな叫び声をあげる。しかし、彼らの抵抗というのは、あくまでも現実ではなく、ファインダー越しでの「フィクション」にすぎない。でも、そこに美しさがある。現実は自分たちには厳しいということを彼らは自分自身で十分理解し、だからこそ映画という空想の世界に思いを馳せるのだ。このシーンのカタルシスはなんと表現できるんだろうか。
この映画が、現役の中高生とかにはあまり受けず、というか意味がわからない、という意見が多いらしいけど、いい歳こいた大人から絶賛されるというのは、多分、多くの人達がある年齢を重ねていくと、周りとの関係とかからも、自分の限界とか才能とかそういうものに、ある種の諦めというか、そんなものだ、というような諦めみたいなものを感じるようになるからかもしれない。その自分の姿や思考を、この映画に登場する登場人物のいずれかに投影してしまうのではないか。
ちなみに、ボクは映画の後に、小説の方も読んだのだけど、正直、小説はそこまでではなかった。