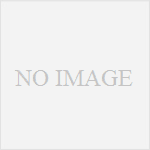これがカッコいい時代があったんだ、多分〜「青年は荒野をめざす」
展開が早い。今読むとかなり無茶苦茶という印象。一瞬、これは青春小説の態を装ったギャグ小説なのではないかとも疑いたくなる。
主人公ジュンは本物のジャズを追求して日本を出る。そして、日本ではとてもじゃないが体験できない稀有な体験を経て、少しずつ成長していく。その成長とは、固定観念やルールを解き放ち、ある道徳観では悪とされることが、時には善であるというようなパラダイム転換を識るということなのだろう。
ストックホルムでは秘密の社交場で、著名芸術家たちが規範から解き放たれる様を見せられ、ジュンは「違う」と、大胆にも自らステージに上がり、演奏を行い、それがその地下の混乱を招く。ジュンとケンは、そこからあっさり脱出して、ストックホルムを後にしてしまう。
とにかく展開が早い。ドラマ的というか、その展開の早さがとてつもない安っぽさというか、嘘っぽさを醸し出してしまう。正直、今、読むと笑える。ジュンはあまりにも短絡的すぎる。
ジャンルは違うにせよ、沢木耕太郎の「深夜特急」の旅が、よく読んでみれば、たいした事件は起こらないのだけど、異国の地でのちょっとした出来事や気づき、心境の変化というものを、きちんと書き留めることで、「旅」への憧れを掻き立てるのとは、まったく逆で、この小説では、事件の勃発と、その事件を乗り越えていくことでの、直截的なわかりやすい青年の成長の様を描いている。60年代、70年代においては、この本が青年を旅や海外へ駆り立てたという話も聞くが本当なんだろうか。
海外で起こるあり得ない事件の数々に、自分もあんな体験をしてみたい、と当時の若者たちは考えたのだろうか? 世界が物凄く身近に近くなってしまった現代だと、ジュンみたいな青年が近くにいたら迷惑で仕方ないかもしれない。
表現のレベルにおいても、あまりにも低俗的な悪趣味なものが多く、時代を感じる。早川義男は、「かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろう」と看破していたけれど、多分、この小説が採用している言い回しや比喩、レトリックが、カッコいいと思われた時代もあったんだろうと思う。
でも、そういう時代の表層的な「かっこよさ」みたいなものが、時代遅れになると、途端に「かっこ悪い」以外のなにものでもなくなるということが、この小説には端的に表れている。
なかなか最近ではお眼にかかれないような表現を引用しておこいう。
これはジュンの初体験のシーンである。青年の冒険小説にとっては、なかなか重要なシーンなのでははないかと思う。
p.98
ジュンは、体を起こした。ベルトをはずし、スラックスのジッパーを、力をこめて引きさげた。ブリーフを分けて、彼は自分の熱いトランペットを摑んだ。それは、堅く、生き生きしたビートをきざんでいた。裸の肌に五月のモスクワの夜気が爽やかに感じらやた。二十歳のジュンは、ゆっくりと、リューバの体を引き寄せた。
「自分の熱いトランペット」って。あまりにも下衆というか、今時、スポーツ新聞の三面エロ記事、風俗体験談でさえ、出てこないような安いメタファー。ビートを刻むとか、メタファーでうまく文章を装飾しようとして、さらに恥ずかしい感じがひしひししてくるじゃないか。
でも、これがカッコいいとされた時代があったのだ。たぶん。僕は知らないけど。そういうものの総カタログとして読んでみるのも面白いのではないか。
スポンサーリンク
スポンサーリンク