ほんとに愛おしい小説「惜日のアリス」
惜日(せきじつ)のアリス 
この小説はまじでやられました。傑作だと思います。
同タイミングで、村上春樹の新作も発表され、もっぱら小説や文学の話題は、そっちに完全に持っていかれてた感もあるけれども、いやいや、実は、現代日本文学においてものすごく重要な作品は、そんな喧噪の外側でこっそりと産み落とされていたのです。
読んでて嬉しくて嬉しくて。こういう気分になれた小説は久しぶりでした。
中森明夫は、「村上春樹と高橋源一郎以降、途絶えたポップ文学を1984年生まれの青年が更新する。」と、この作者を絶賛していたわけですが、まさにこのデビュー作は、村上春樹、高橋源一郎の系譜を受け継ぐ作品だと言えます。村上春樹、高橋源一郎が好きな人なら、読み始めればきっとその意味に気付くと思います。
彼らのデビュー作が、いずれも「言葉」で世界を語ることの困難さと、それを自らが引き受ける覚悟を、その小説の根本的な主題に置いたのは、決して偶然ではありません。言葉で世界に向き合おうとする作家が、その覚悟を突き詰めた結果、言葉そのものについて語らずをえなくなってしまうのはいさしかたないことなのではないでしょうか。そう、彼らの小説は、物語の前に、言葉があったのです。言葉について言葉で語るということの不毛さや困難さに、最初に取り組んだ、取り組まざるをえなかったということでしょうか。
村上春樹は、有名な次のような一節から小説を始めました。
風の歌を聴け (講談社文庫) 
「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」
僕が大学生のころ偶然知り合ったある作家は僕に向かってそう言った。僕がその本当の意味を理解できたのはずっと後のことだったが、少なくともそれをある種の慰めとしてとることも可能であった。完璧な文章なんて存在しない、と。
しかし、それでもやはり何かを書くという段になると、いつも絶望的な気分に襲われることになった。僕が書くことのできる領域はあまりにも限られたものだったからだ。例えば象について何かが書けたとしても、象使いについては何も書けないかもしれない。そういうことだ。(「風の歌を聴け」)
今でこそ、この手の文章はそう珍しくはありませんが、少なくとも村上春樹以前にこのような文体は存在しませんでした。この冒頭の数行を引用するだけでも、この頃の村上春樹の文章の乾いた軽さみたいなものは十分に伝わるでしょう。その後、何度も何度も登場する、文体がすでにここに存在します。そして、象徴的なのは、文章を書くということについて、語るということについての自己言及から小説が始まるということです。村上春樹には、書きたいもの書こうとした世界があったわけですが、おそらくそれを表現するのに適した文体や小説スタイルというものが日本の小説にはなかった。だから、春樹はその文体を自ら作り出す他なかったのでしょう。明治期の言文一致運動の際に、作家たちが「内面」や「自然」というものを表現しようとしながらも、それらを語る文体がなかった時と同じように。
村上春樹が鮮烈なデビューを飾ってから2年後、高橋源一郎は、春樹のやり方とはまったく違う方法で、「言葉」を中心に置いた小説でデビューを果たします。
それは「名付ける」という行為から始まる小説でした。「名前」がなくて何かしっくり来ない恋人たちは、自分たちにふさわしい名前のつけ方を考え出す。お互いがふさわしい名前を命名し合うのです。
さようなら、ギャングたち (講談社文芸文庫) 
そうやってわたしたちは名前をつけるようになった。
わたしたちは自分の名前をつけてもらいたいと思う相手に「わたしに名前をつけて下さい」と言う。
それがわたしたちの求愛の方法だ。
わたしは何度も名前をもったり、喪くしたりした。S・B(ソングブック)に会うまで、ずっと長い間、名前なしですごして来た。
何度も名前をかえているうちに、わたしたちはだんだん慎重になってゆく。
4
「君に名前をつけてもらいたい」とわたしはかの女に言った。
「いいわ」とかの女は言った。
そして
「わたしにも名前を頂だい」とつけ加えた。
ミルクとウオツカのカクテルを飲んだ「ヘンリー4世」はバスケットの中ですやすやねむっていた。
わたしたちは初めて愛し合った後で、心地よく抱き合っていた。
わたしは自分の机に行って、原稿用紙にかの女の名前を書いた。
ベッドの上でかの女はむこう側をむいて、小さい手帖にわたしの名前を書いていた。
わたしはかの女の裸の背中をながめていた。
わたしは女の背中がそんなにきれいなものだとは知らなかった。
5
かの女はわたいの書いた原稿用紙をうけとって読んだ。
中島みゆきソング・ブック
「ありがとう」とかの女は言った。
こうやって引用して自分で文章を書き写してみると、すごくよくわかるのですが、やはりこの小説の言葉の強度というのは凄まじいものがあります。これは少なくとも小説、長編小説の言葉ではなく、完全に詩の言葉です。一つ一つの言葉の選び方、表現の仕方、改行の取り方、何から何までおそろしく神経を使って丁寧に丁寧に書かれています。言葉が言葉として純粋に、必要以上の無意味な「意味」を帯びないようにという厳密な配慮があります。
そして、村上春樹、高橋源一郎とはまた違ったスタイルで、坂上秋成は「言葉」について語りはじめます。
「惜日のアリス」では主人公が小説を書こうともがき苦しむ様がそのままが文体に表現されています。小説の前半、まだ主人公は、自分が何を書きたいのかがわかっていません。ただ、それでも何かを書きたい、その衝動だけで小説を書いています。そして、アルバイトで働く映画館の館主の「おばあさん」に、自分の書いた小説を見せます。
「不用意なんだよ、おまえの言葉は。危うさや、繫がりを持たせることにつきまとう困難、そういったものをあまりに安易に捉えている。これはね、小説の言葉になっていないよ」
小説の言葉・・・・・ それが一つ特別なものであることはわたしにも理解できるのだった、これど、それは感覚のレベル、なんとなくの領域の話で、どこが他の言葉と違うものなのかを説明することはできないし、創ることによって差異を浮き彫りにすることもできず、ああ、自分の内側を走る神経の一つ一つがか細くなっていくような錯覚、わたしは困惑の表情を見せているはず、おばあさんに対して、きっとそこにはすがる様な視線もまじっているはず、ちくしょう、なんて情けねえんだ。
それでも、ただしょげてるだけというわけにはいきません。再びの機会のことを思って、わたしは懸命に声を絞り出します。
「また書くのです、わたし、そうしたら、また見てください、感想を、ください」
文体はたどたどしく、しかしそこには書くことの衝動に突き動かされる主人公の純粋な気持ちが描かれます。それは少し痛々しくもあるのですが、僕はとても美しいと感じました。なんでこんなにこの文章は愛おしいのでしょうか。
高橋源一郎が詩の言葉が持つような強度で小説を書こうとしたのとは違い、この著者、いや主人公は、書きたいこと語りたいことの衝動そのものの押さえきれなさを、過剰な言葉で表現するのです。それはこの小説の前半の奇妙な文体から立ち現れてきます。
日本語はとくに語尾の処理が難しい言葉と言われてますが、この小説は、それを極めて意識的に扱うことで、なんとも言えないたどたどしさと、押さえ付けられない想いが表現されます。
たとえば、次のような文章。
算法寺はとっても効率的で合理的な人なのでした。ちゃんと、積み木を下から順番に一つずつ組み上げていく。「丸い積み木をお城のてっぺんに置いたら素敵かも!」というような直感に基づく判断はしない。そのことは、とても人間を大事にしているように思えるのでした。わたしの感覚はわたしだけのもの、なので、全然違う感性を持っている人に言葉は届かない、けれど、算法寺はちょっとだけ外側から論理という武器を使って攻め込むので、それは読んでくれる人の脳みそを信頼しているということに繫がっているはずなのだ。
「です/ます」文体の中に、突如登場する「なのだ。」という語尾の違和感。主人公はこんな風に語りながら、一方で、恋人である「算法寺」が時折会話の中で使う「のだ」に敏感に反応して違和感を感じるのです。「のだ」についつい嫌悪感を感じてしまいながら、自身の文体は定まらず、「のだ」や「ですます」などが混在し、とてもたどたどしいものになっています。そのたどたどしさが、なぜかこの主人公をより一層愛おしく思わせるのです。
「詩は芸術だ」、と算法寺は言いました。
「そうである以上、俺が目指すべきものは偉大なる芸術家だ。両の腕から言葉を繰り出し、観客を魅了し、高みへと近づく。陳腐な言い方かもしれないが、俺が詩を書く理由はこれしかないのだ」
「のだ、って言わないで。ねえ、小説も芸術なのかしら」
小説としては、15年後の二部では、松浦理英子っぽい世界が展開されたりしていくわけですが、ただ、僕はこの小説の帯にあるような「新たなる「家族」と「性」の物語」というような捉え方は、この小説の面白さの中心を少し外してるように思うのです。もちろん「ビアン」の世界は、いかにも現代的で、またその世界を違和感なく素直に受け入れる莉々花という少女がとにかく可愛くて仕方なかったりもするのですが、でも、この小説はそこよりも、やはり主人公と「言葉」との関係にこそ、面白さがあるのではないかと思います。
言葉をより流暢に扱えるようになり、職業作家としても活躍するほどになった主人公は、後半、さまざまな語りのスタイルを取ります。
USTREAMでのDJ的な語り口があれば、詩のような言葉、メールで使われる言葉。主人公が使う言葉は、前半のたどたどしさが嘘のようです。前半と後半ではまったく別人かのような断絶があります。しかし、器用に言葉を扱えるようになったが故の誤摩化しが芽生え、それが主人公とナルナとの関係を変えてしまう、というのはなんとも象徴的です。もっと言葉を美しく、もっとうまく語りたいと願っていた少女は、その望みを叶えたようにも思えたわけですが、言葉を紡ぎだすための葛藤や苦しさを忘れ、今の居心地の良い世界を守るために、自身の過去、自身の言葉を否定してしまう。でもナルナは、そんな主人公の姿を見て、主人公にもう一度、言葉を愛し、言葉を取り戻してもらおうと、主人公の元を去る。そして、主人公は、自身が紡いできた言葉/紡ごうとしてきた言葉がどんなものであったかに気付かされるわけです。そう、性や家族が問題になっていそうに見えながら、この小説はずっと最後の最後まで「言葉」について考え語り続けているのです。
< <あたしは、彼にあんな言葉を投げつけるべきじゃなかったのね>>
< <ねえ、あなたは頑張って大人になろうとしてきたわ。実際にそれで上手く生活は回っていた。けれどあなたの中の少女は生きているじゃない。彼女がいたからこそあなたは言葉を今も愛している。小器用になることと大人になることは全く別物だわ。少女を生贄に捧げて、言葉を暴力として人にぶつけて、それを綺麗な世界として扱おうなんて、何ともふざけた話じゃない?>>
< <あの子が羨ましかったわ。枷がないんだもの。自由に書き散らして文句を言われないんだもの。好きな言葉だけを人に向けて喋り続けることができるんだもの。けれどそうじゃないのよ、本当は。彼女には彼女の闘いがあった。夢の国で、おとぎ話の中で、足りない頭を全力で回転させていろいろなものに抗っていく意思があった>>
< <あなたは大人びた語り口で、論理的で丁寧でよくまとまった言葉で、周りの人たちに話しかける。大した喧嘩も起こりはしない。だって大人なんだもの。そうやって痩せ細っていくんだわ。けど、みんなあなたのことが大好きだからそれを咎めもしない。上手い具合に続いていく。言葉を愛し、あなたと分かり合おうと望む人がいても、あなたは自分の世界を守ることを優先して傷を負わせてしまう。ヘテロからビアンになって、多くの人が苦しむはずの事態も、素敵な仲間たちのおかげであなたには降りかかってこない。ねえ、ここは随分とあなたに優しい場所ね、だからこそ、あたしと莉々花は別のところに行かなくてはいけなかったの>>
(略)
< <・・・・・・・・・・・・彼女の言葉はちらばったまま輝いていて、けれどそれをまとめることを諦めていいなんてことはなく・・・・ああ、何て言えばいいのかしら・・・・私が今紡ごうとしてりう言葉はバラバラで、だけど繫がっていて・・・・正しい呼称が見つからないわ>>
< <それをあなたは小説と呼んできたんじゃないの?>>
< <そうね。そうかも、しれない。それが小説だわ。あたしが初めに愛した小説は、確かにそういうものだった気がする>>
< <名前なんて本当はどうでもいいのよ。この世にあるすべての名前が、意味を失う日が来てもあたしは一向に構わない。小説でもエッセイでも批評でも好きにすればいい。その中に、ちゃんとあの子が住んでいるなら、言葉はきっと華やかなものになっているはずでしょう?>>
さて最後に、ちょっと視点は変わりますが、この一節を引用しておきます。この語り口、内容は、そのまま村上春樹と高橋源一郎を思い起こすものではないでしょうか?
いきなり朗読に入るような気分じゃないのよ、ごめんなさい。なにか、お話しましょう。なにがいいかな・・・そうね、ギャングの思い出とかはどうかしら。かつて、ギャングについてとても華やかな文章を書いた小説家がいたわ。初めてその小説を読んだ時、私は大声で泣いた。
それほどに圧倒的な文章だった。ああ、これでもう私はギャングについて何一つ語ることができなくなってしまったのだって、そう考えた。けれどギャングが一人しかいないなんて誰が決めたのかしら? 世界には無数のギャングがいて、きっとその小説がすべてのギャングを描き切ったわけではないはずなのよ。私には私のギャングが、あなたにはあなたのギャングが・・・
そう思うと、体の中心、おへその下の辺りから力が湧いてくるのを感じた。書かなければいけない、語らなければいけないって、強く強く感じた。だから私は今もギャングのことを考え続け、暇を見ては子どもにギャングのお話を聞かせてあげてるの。私だけが知っている、あまりにも美しいギャングのお話を・・・
(略)
今日は少し声がクールですね、か、ふふ、ありがとう。家族が家を空けていてね。今は一人きりだから、テンションもいつもと違うテンションだから、普段言わないような台詞も言っちゃおうかな・・・・・・・・・・・・・・・・ 愛してるわ。心の底から、顔も見えないあなたたちのことを、愛しているわ。ありがとう。これまで私に関わってきてくれて、本当にありがとう。細い回線だわ。今、停電が起こったら、もう二度とあなたたちと会うことはできなくなるかもしれない。けど、そんなことになっても私は忘れない。パソコンの画面の右端に出ている小さなチャットボックスの中にあなたたちがたくさんの言葉を書き込んでくれた事実を、決して忘れたりなんかしない。


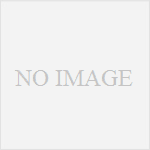







コメント
ほんとに愛おしい作品が今後も書けるのかな!?
ネットでいろんな感想を見ていると、集約されていく感想です。
こちらの感想との正反対のサイトがあったので、
リンク貼っておきます。
http://www.birthday-energy.co.jp/
個人的には、初小説にしては丁寧な作品ですね。
次の作品を期待したくなります。