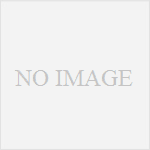辞書作りに青春を捧げた人たち「舟を編む」に感動した
素晴らしい映画だった。
観てない方はぜひ観るべき。じわっと暖かい感動に浸される。無理やり泣かせよう、感動させようというような派手なストーリーも演出もないけど、一つの一つのシークエンス、登場人物たちの表情や所作、これらの積み重ねがとにかく素晴らしい。僕は原作を読んでないので原作との比較はできないけど、映画としてもしっかりと完結していて十分におもしろく感じられた。
舞台は1994年から始まる。まだ、インターネットを利用している人も殆どいない、携帯電話も本格的には普及していない、そんな時代。ある出版社で新たな辞書「大渡会」を編纂するというプロジェクトが始まる。
辞書を編纂するのには膨大な時間と人的作業が必要とされる。大渡会のコンセプトは「今を生きる辞書」。ら抜き言葉や、「憮然」などの誤用や、本来の意味ではない用途が広まってきている言葉、あるいは「チョベリグ」「ダサい」などの若者たちが好んで使う今の言葉、これらを盛り込んだ新しいコンセプトの辞書。それが大渡会だ。
本編の中で他社の辞書がどれだけの年月をかけて作られているかが説明されるくだりがある。正確な数字は忘れてしまったのでネットで調べた年月を書いてとくと、広辞苑は25年、大辞林は28年月もの歳月がかかっているらしい。今時、こんなにもの年月をかけて一つのもの作り出すことも稀だろう。今はなんでもすぐに真似される時代だ。商品のライフサイクルはどんどん短くなっている。コンビニの商品の六七割はにねんで入れ替わるらしい。そんな時代に、何十年もの年月を要する辞書編纂という仕事は異色だ。
辞書の編纂というものが、本当に途方もない作業なのだということは、この映画での作業の光景を観ても、伺い知ることが出来る。
辞書に入れる言葉の元ネタ作り「用例採取」に始まり、どの言葉を辞書に載せるかの取捨選択(「見出し語」の決定)、これは他社の有名辞書二つから、どちらにも掲載されてるもの、どちらかに掲載されてるもの、どちらにも掲載されてないもの、という区分を一つ一つ辞書をめくっては印を付けて行くという作業だ。これに従事してるとページをめくり過ぎて指紋がなくなってしまうほどだという。
そしてそこから訳語を付けて行く。他社辞書を参考にするのではなく、きちんと自分で考えた訳語をつけなければならない。
映画では「右」にどんな訳語をつけるかで悩むシーンが登場するが、右というたった一つ当たり前に使われる言葉でさえ、トートロジーにならずに説明するということは難しい。
この後もまだまだ膨大な作業が待ち構えている。辞書に見落としや間違いがあっては会社の信用にも関わる大問題だ。Wikipediaのような訳にはいかない。何度も何度もチェック、校正が繰り替えしが延々と続く。
なにせ最終的に見出し語となる言葉は20万語を超える。これを人の手で一つ一つチェックしていくのだから、本当に辞書編纂というのは、小さな小さな人の手で漕ぐような舟で途方もなく広大な海原に乗り出していくようなものだ。
そんなプロジェクトに人生を捧げた人たちが描かれる。これが熱い。そこには血や汗や涙はないかもしれない。でも、ものすごく熱い。黙々と辞書をめくる人たちの姿に僕は何度も何度も胸を打たれる。
人とのコミュニケーションがうまくとれず、殻に閉じこもってた主人公馬締(松田龍平)は、辞書編纂に関わり、少しづつ成長して行く。その姿にも心が温まる。馬締がかぐや(宮崎あおい)に恋するシークエンスもとても良かった。馬締の真面目さと不器用さ、それを赦すかぐやの優しさ。とてもうまく表現されてる。
また、周りの人たちの変化していく、その様も少し嬉しくなる。
膨大な年月のかかる辞書作りに半ば呆れつつ少し冷めてたいかにも現代的な西岡(オダギリジョー)は、周りの熱に感化されていくし、女性誌の編集部から大渡会の編集部に移ってきた岸辺みどり(黒木華)は、当初は戸惑いながら、徐々に溶け込み、辞書編纂に喜びを感じるようになっていく。服装が地味になったり、シャンパンしか飲めないとわがまま言ってたのが、居酒屋でビールを一気に飲み干すまでに逞しくなっていく。
ここで描かれているのは、青臭いかもしれないけど、ある種の青春なんだろうと思う。周りからは冷ややかな目で見られようが、自分の信じるものに突き進み、そこに情熱を注ぎ込む。
その時は迷い苦しみ悩み、でも、振り返ったときにはとても遠く懐かしく感じられる。その最中にはそれとは気づかないけれど、ある一定の距離(時間や場所)を経ると、あああれは青春だったんだなと感じられる。青春はそういうものなんだろうと思う。
僕はふと自身の創業からのことを思い出してしまった。僕らの創業も1995年で、この映画の始まりの舞台とほぼ同じ時期だということもある。何かのトラブルで皆で泊まり込みで作業に当たったことも何度もあったし、家でも朝方まで仕事に追いかけられたことも少なくはなかった。今思えば、若かったからこそ出来たということかもしれないし、なにも知らなかったからこそ出来たということもあったのだろう。
大渡会の編纂に自分の思い出なんかも重なって、多分、より一掃、思い入れがつよくなってるということなんだろうと思う。
そういえば、辞書をめくることをしなくなったのはいつ頃からだろうか。僕は一人暮らしの時でも国語辞典と広辞苑は必ず手元に持っていた。馬締のようや持ち歩きはしてなかったけれど、本を読んでてわからない言葉が出てくれば必ず調べてた。でも、いつ頃か、それをインターネットの検索で代替えするようになっていった。今は手元にあるスマホで手軽に調べてる。めっきり辞書は引かなくなった。
今、辞書作りはどうなっているのだろうか。いくらWikipediaが便利だとは言っても、実際の辞書の信頼感や質には敵わないはずだ。ネットを探せば、どんな言葉でもどこかの誰かが説明してくれてはいる。後は、その説明や訳語を信じるか信じないかだけの問題だ。でも、だからきちんとした辞書が不必要なわけではない。やはりプロのてでしっかりとした編集、校正がなされた辞書は必要だと思う。
しかし、この映画での辞書編纂の様子を観ると、もし自分が出版社の経営をしてたら、これだけの時間と労力をつぎ込んで、どれだけの利益が得られるのだろうかと疑問に思うこともあるだろうし、出版社にとっての営利事業としては辞書はなかなか難しいのかもしれないなぁとは思う。少なくとも紙の辞書は使い勝手や作る側の手間を考えてもかなり難しいことだろう。
でも辞書がない社会や世界というのはそれは凄く哀しい。
あの辞書の厚みや圧倒的な存在感。見てるだけで世の中にはこれだけの言葉があるのだと何か不思議な感慨みたいなものを抱いてしまう。何を探すでもなくページをめくってみても、そこには自分が知らなかった言葉や用例が必ずいくつも見つかり、世界の広さや深さを辞書を通じて味わうことができる。
今の子達は殆どが電子辞書なんだろうか?
スマホの辞書アプリだろうか。 電子辞書もアプリも便利だとは思う。でも、宗教的ではあるけと、辞書はあの大きさや厚みや、存在感も魅力の一つだと思うし、あの紙の手触りや、ある言葉を探したときにまた別の言葉に出会ってしまう偶然や驚き。紙には紙の良さがある。また、紙の辞書は、無尽蔵にページ数を増やすこともできないし、広辞苑でも大辞林でも物理的に文字数や見出し語数は決められている。おそらく、その制限に合わせるということも辞書作りの大変な工程の一つでもあるだろうし、そういう制約があるからこそ、研ぎ澄まされた言葉が選ばれ、語訳がつけられるのではないか。
そんなことを考えると、時代の流れとは故、紙の辞書がこのまま廃れていってしまうのは、やっぱり凄く淋しいことだ、僕は思う。
今もどこかで、人の言葉に聞き耳を立て、用例採取をしている人たち。失敗が許されない紙の辞書だからこそ、何度も何度も何万もの言葉の校正をしている人たち。
そんな辞書を作っている人たちに心から敬意を評したいと思う。
スポンサーリンク
スポンサーリンク