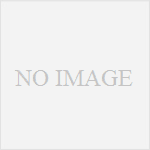フェチ小説と言えば、川端康成「眠れる美女」
谷崎の「鍵」を変態フェチ小説として紹介したばかりだが(谷崎フェチズムの極み「鍵」 | papativa.jp)、変態フェチともなると、川端康成も紹介せずにはいられない。
これは川端康成の小説の中でも特別に好きな小説の一つ。川端康成を初めて読むなら、「雪国」や「伊豆の踊り子」ではなく、ぜひ、「眠れる美女」を手にして欲しい。
しかし、老人はもう既に男ではなくなっているので、ただただ添い寝したり、その肢体を愛でたり、肌に触れたり、それらを愉しむことしか出来ない。
このシチュエーションの異常さ、奇妙さは何だろう。ものすごく現代的な設定とも言える。
今でこそアニメや人形への「愛」や「性的興奮」なんてのは珍しくもないだろうけど、この作品が書かれた当時では、この一方通行的で且つ、どこまでも満たされることのないやり切れない設定は、やはりかなり偏執的だし、異常だったんではないかと思う。
この小説は川端康成62歳の作品だけど、これはおそらく、本人自身の欲望・願望を全面的に注ぎ込んだんじゃないかと思う。執筆していた時期や年齢なんかを想像すると、これから本格的な老いを迎えることへの恐怖や絶望みたいなものがこの作品誕生の源泉になったんではないだろうか。でないと、なかなかこんなシチュエーションを思いつけるものじゃないんじゃないか。
今、読み返してもこの設定は全然色褪せない。むしろ新鮮にさえ感じる。川端康成の筆致も、円熟期を迎えて滑らかであり、また静かに響いてくる。素晴らしい文章だ。下手すればただの下品になりそうなところだけれども、なぜかむしろ上品にさえ思えてしまう。
主人公の江口老人は、「眠れる美女」の宿で、少女との一夜を過ごしながら、自身の過去を顧みる。ふとした少女の匂いや仕草から、江口を通り過ぎた過去の女や、自身の娘との関係などが思い起こされる。しかし、それに江口老人がノスタルジーに浸るわけでもなく、ただ過去の亡霊として脳裏に浮かび上がるその情景をたんたんと描く。その描写にのめり込んでいくと、あたかも自分自身が老いて、そして老いた自分が過去の若かりし頃の自分を思い出してるかのような錯覚に襲われる。
この小説が単に戯画的なものにならずに成立してるのは、老人の眼前の状況の異常さに対して、そこ回想にリアリティがあるからではないかと思う。
とにかく読み始めると、最初のよくわからないがなんとも魅惑的な状況をもっともっと知りたくなり、やめられなくなるだろう。そして、どんどん引き込まれ、まるで江口老人のようにその世界に引き込まれていくだろう。
スポンサーリンク
スポンサーリンク